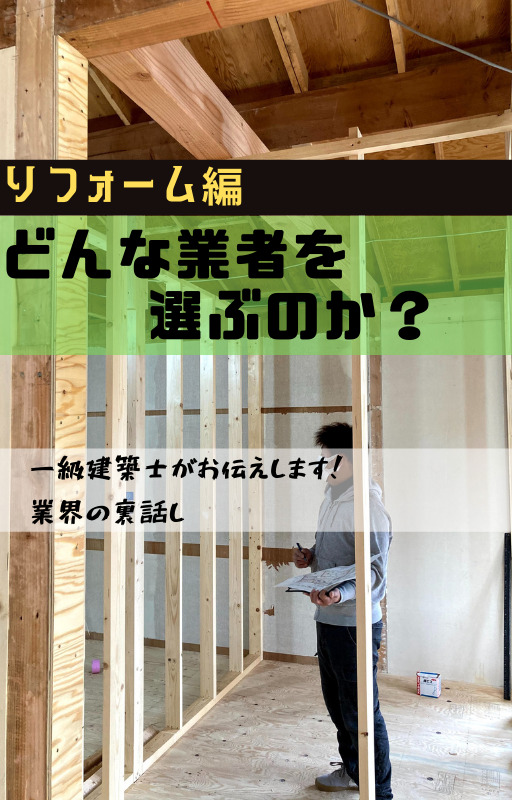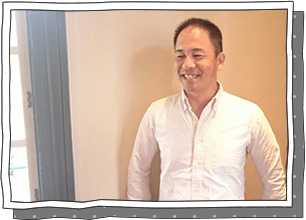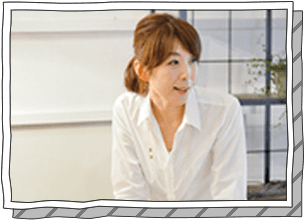遺言に付言事項は絶対に必要だと思います。
遺産相続について調べている中で、どうせなら遺産をどのように相続していくか?というお金に関することだけではなくて、他にも伝えておきたいことが出てくるはずです。
ただ手紙として残すのも良いですが、そのような場合には付言事項を活用すると良いでしょう。
この記事では、遺言と合わせて残しておくとよい付言事項に関して、次のような内容を解説します。
- 付言事項の読み方
- 付言事項とは?
- 付言事項の持つ効力
- 付言事項の記載例
付言事項に関して知識を身につけ、きちんと自分の言葉を正式な形として残しておけるように準備を進めましょう。
付言事項読み方

付言事項という漢字の表現や、具体的な意味は分かったとしてもいざ自分で打とうとすると変換で出てこず、結局コピペしてしまうこともあると思います。
「ふごんじこう」と読んでしまいがちですが、正しい読み方は「ふげんじこう」です。
せっかくなのでこの機会に覚えておきましょう。
付言事項とは

遺言を残す際に作成する遺言書は、法的な効力を持つ法定遺言事項と、法的な効力を持たない付言事項に分けられます。
付言事項に法的な効力はありませんが、相続人に対して伝えたい言葉、残しておきたい言葉を伝えるために必要不可欠です。
残した遺言が効力を発生する際に、残した本人は既にいない状態なのでどのような思いで遺言を残したのかが伝わらなくなってしまいます。特に法的な効力がある部分は、身分・財産・相続に関する部分なので、結果だけを見てしまうとギクシャクしてしまう可能性があります。
トラブルを防ぐためにも、「なぜ」、「どういう考えで」法定遺言事項に記載の結論を導き出したのかを伝える必要があります。その役割を担っているのが法的には効力がなく、不要だと感じられることもある付言事項です。
付言事項 効果

付言事項には、相続によって生じる可能性があるトラブルを未然に防ぐ可能性があります。
相続の結果だけでなく、そう決めた過程を残すことで故人の考えに思いを巡らせることができ、多少相続の結果に納得がいかなくてもトラブルに発展させない場合もあるでしょう。
特に、遺言に記載されている内容とは関係なく存在する権利を超えて遺言に記載している場合、その権利を主張されるのを防ぐ効果も期待できます。
付言事項としての記載をわかりやすくし、その効果を最大限に発揮させるためには法定遺言事項と分けてまとめて書くのが良いでしょう。自分で書くタイプの遺言であれば、遺言事項を書き終わった後に「付言事項」ということを明記して書くと明確です。
付言事項は法的な効果を持たないので、どんなことを書いても問題ありません。一般的には、残された人たちへの比較的ポジティブなメッセージが多いですが、愚痴や悪口を書くことも可能です。
しかし、付言事項に悪口や愚痴を書くことは相続のトラブルを助長させてしまうことになりかねないので、特定の人物を明示してネガティブなことを書くのは、なるべく避けておきましょう。
付言事項の記載例
付言事項として遺言書に記載する内容の具体例としては次のようなものが挙げられます。
- 相続分を指定した理由
- 自身の葬式や法事に関する依頼事項
- 家族仲良くやっていくようになどのメッセージ
- 家訓や家業の今後に関する依頼事項や希望
- 移植できる臓器などの扱い
これらに関して自分がどのように考えているか?という点を記載し、できるだけ残された家族が希望を聞いてくれるようにしておきましょう。
付言事項 まとめ
付言事項は聞きなれない言葉ですが、遺言書に記載する内容の中で法定遺言事項以外の法的な効力を持たない部分です。
残された家族に対するメッセージを残すことで、相続に関するトラブルを未然に防いだり、自身が希望することを死後に実施してもらうために利用できます。
法的な効力はありませんが、残された家族に想いを伝える機会は多くありませんので、遺言を残す際にはその結果だけでなく、付言事項も合わせて記載しておくことをおすすめします。
無料プレゼント
無料のメルマガ登録で今すぐ受け取ることができます。
1級建築士が作った!
注文住宅で失敗しない
チェックシート

あなたのお家の
快適レベルは?
『断熱レベル診断』

業界の裏側までわかる
リフォーム業者の
選び方